お役立ちコラム
軽天屋って何?軒天屋の仕事を徹底解説
軽天工事を行うのが「軽天屋」です。
しかしながら「軽天」という言葉自体が一般的ではないことから、それがどんな仕事なのかをきちんと理解している方は非常に少ないのが現実です。
ここでは、軽天屋がどんな仕事をするのかを詳しく解説し、軽天屋に求められるものも併せて紹介しています。
目次
軽天屋とは

軽天屋が手掛ける「軽天工事」というのは、その名の通りに軽量鉄骨材を使用して、天井や壁の骨組みをつくる作業です。
建物の建設に鉄骨材が使用されるようになったのは最近のことで、軽天屋という職人が必要になったのは1975年頃。
現在が2021年なので、まだ半世紀も経っていません。
それまでほとんどの建物は木造で建築されていて、木工事を専門とする大工さんが木材を使用して家などの骨組造りを行っていました。
鉄骨材は不燃性であることから、防火性も高く、加工に時間もかからないことから、建築材料としては非常に重宝されるようになりました。
また、材料費や人件費などのコストも抑えられることから、軒天工事の需要は一気に高まりました。
しかし、これまでの木材から鉄骨材を利用するには、施工に関する知識や技術も必要となります。
それを専門に行う軒天屋が誕生しました。
当時はビルやアパートなどの大きな建物の建築で軒天屋が求められていましたが、今では一般住宅でも頑丈な鉄骨材を選択する人が増えたことから、軒天屋の活躍の場所は広がりました。
軽天屋の仕事内容
軒天工事では、主に天井や壁の組み立てをし、ボード貼りなども行います。
つまり、工事が完了すれば見えなくなる部分の施工を行う仕事であり、建物を裏で支えるのが軒天屋です。
「骨組みを造り上げるだけなら、それほど難しい仕事でないのでは?」と考える方もおられるかもしれませんが、目に見えなくなるいろいろなモノに配慮しながら工事を行わなくてはいけません。
したがって、軒天屋には完成図はもちろん、建物建築に関わる細かい部分まで考える計画性も必要です。
一般住宅はもちろん、ビルにもマンションやアパートなどの集合住宅にも倉庫ですら、建物の中には電気や水道などのライフラインが必要です。
それらを引き込むにはたくさんの配線や配管が必要となり、それらは骨組み同様に目に見えなくなるように隠さなければいけないことから、相当な配慮をしなくてはいけません。
建物の骨格を組み立てする軽天屋は、電気工事や水道工事などの設備に関する知識も必要になります。
骨組みは多くの工事に絡んでくるため、ちょっとしたミスも許されない大変な仕事です。
軽天屋に求められるもの
前項でご説明した通りに、軒天屋には軒天工事以外の知識や、計画性と高い技術力が求められます。
もちろん、最初からすべてを身につけることはできないため、軒天屋として独り立ちするには、それなりの経験年数が必要となります。
建築に関するすべての知識を勉強で習得したとしても、現場で体験してみなければ分からないことがたくさんあります。
現場では、計画通りにいかないことは日常茶飯事であるため、軽天屋にはあらゆることに臨機応変に対応できる能力も求められます。
様々な業種と関わり合いをもつことから、コミュニケーション能力も必要です。
また、ほとんどの現場では工程がしっかり決められていることから、作業スピードも要求されます。
現場には骨組み段階でもいろいろな種類の職人が入り乱れて仕事をしていることから、できるだけ迷惑をかけないように段取り良く行動しなくてはいけません。
工事全体の工程を事前にきちんと頭に入れて、トラブルなどが起きた場合も作業が止まらないように自分の仕事を遂行しなくてはいけません。
そのためには、トラブルも想定して、いろいろなパターンに対応できるようにしておかなくてはいけません。
現在では、設計図も現場の工程もコンピューターによって精密につくることができます。
ただし、実際に作業を行うのは人間であり、天候によっても影響を受けることから、計画通りには進まないのが現実です。
そのため、建物の骨格を組み立てる軒天屋には下準備がとても大事です。
技術的な面でも、場合によっては手作業で行わなければいけないケースもあるでしょう。
その時には、高いレベルの技術だけではなく、様々な対応力も求められます。
骨格は土台づくりと同じ建物建築の最初の工事であるため、計画が狂った時には、とにかくスピードが求められます。
それに対応できない軒天屋は、その現場では仕事をまっとうできても、次からは声がかからなくなってしまうかもしれません。
目に見えなくなる骨組みは、間違いが起こると簡単には取り壊して修理・修繕ができないため、慎重さも要求されます。
何かあった時には相当な費用がかかってしまうことから、損害賠償請求を起こされた場合の保険なども備えておかなくてはいけません。
まとめ
軒天屋の仕事は、検量鉄骨材を使用して建物の天井や壁などの骨格と組み立てることです。
建物の骨格は最終的に目に見えなくなりますが、電気や水道などの設備工事に絡み、骨組みには多くの配線や配管なども収めなくてはいけないことから、設備などに関するトータル的な知識も必要です。
また、工事を進めるうえで、いろいろな業種との絡みがあることから、知識や技術力の他にもそれなりのコミュニケーション能力が求められます。
建築工事では計画通りに進まないことも多く、トラブルが起きた時にはとにかくスピードが要求されます。
適当な作業をすると間違いが起きやすく、建物の骨格部分は簡単に修理や修繕もできないことから、慎重さも求められる大変な仕事です。
関連記事
 03-6638-8530
03-6638-8530
受付時間 9:00~18:00 (日曜日定休日)
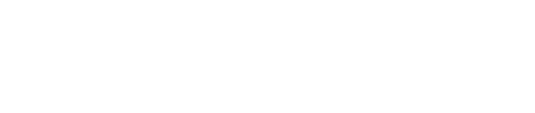
 03-6638-8530
03-6638-8530 見積もり依頼
見積もり依頼





